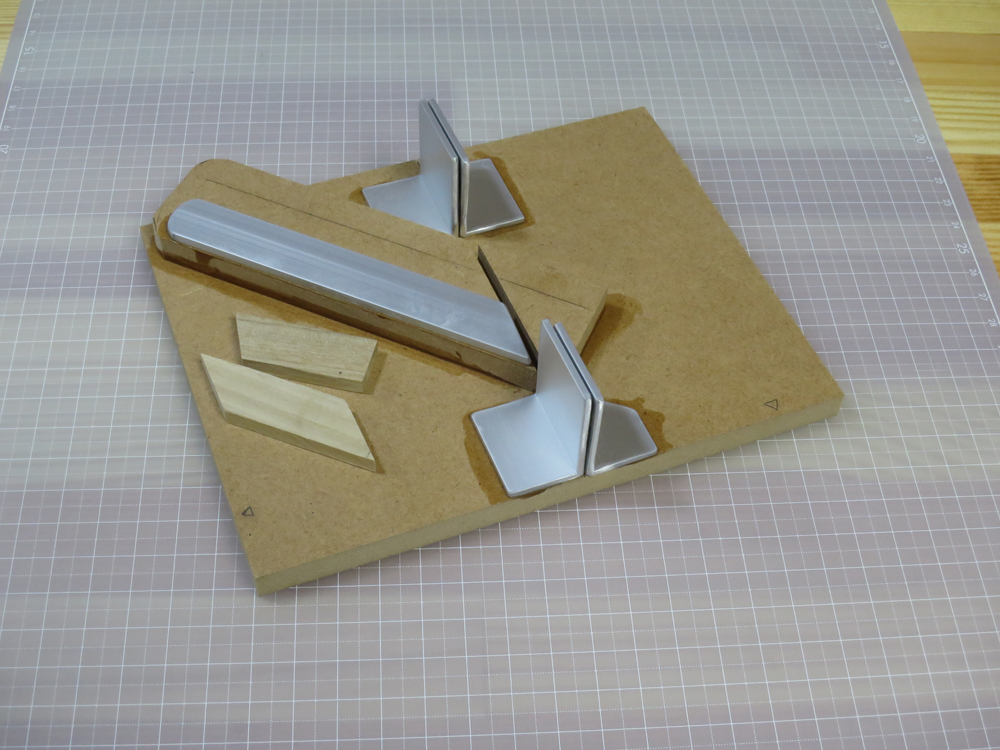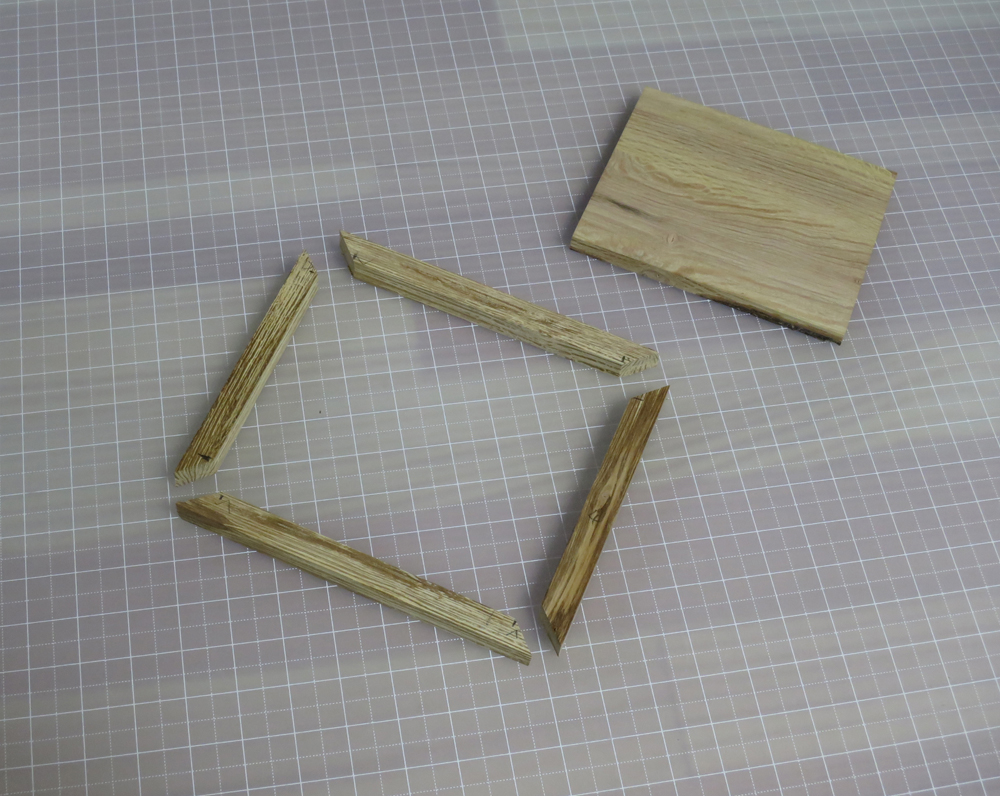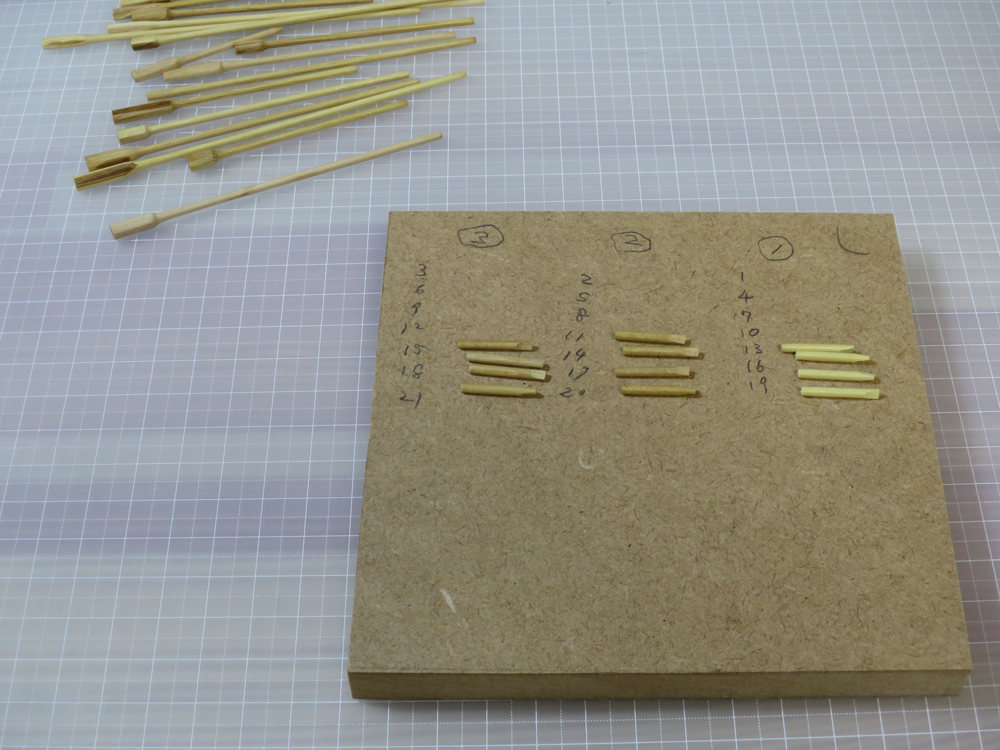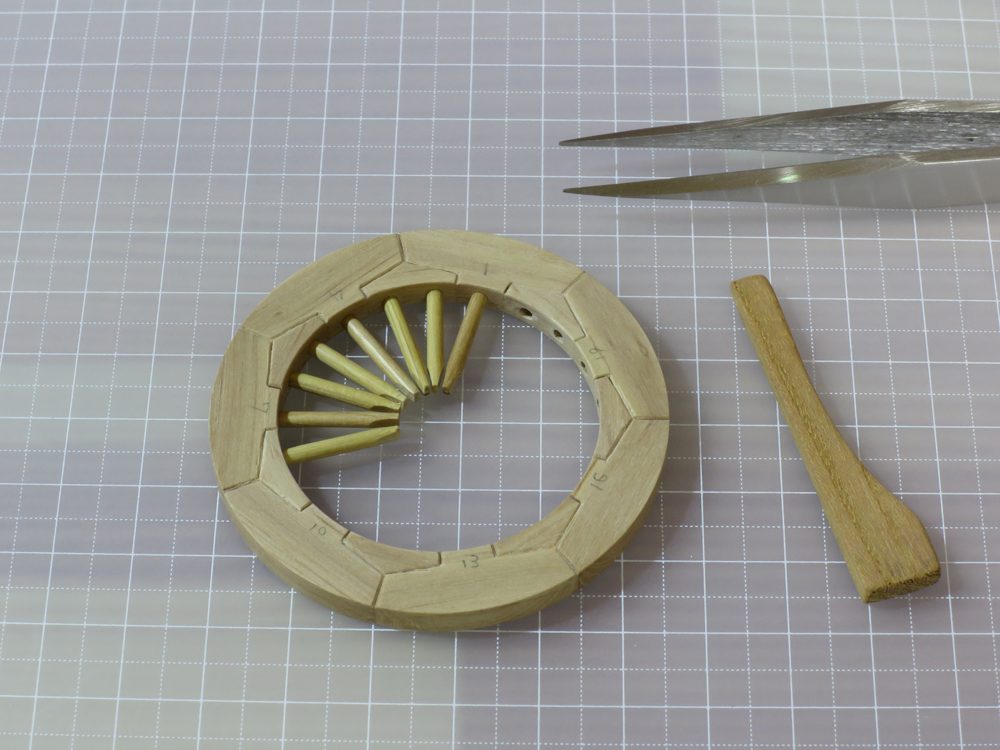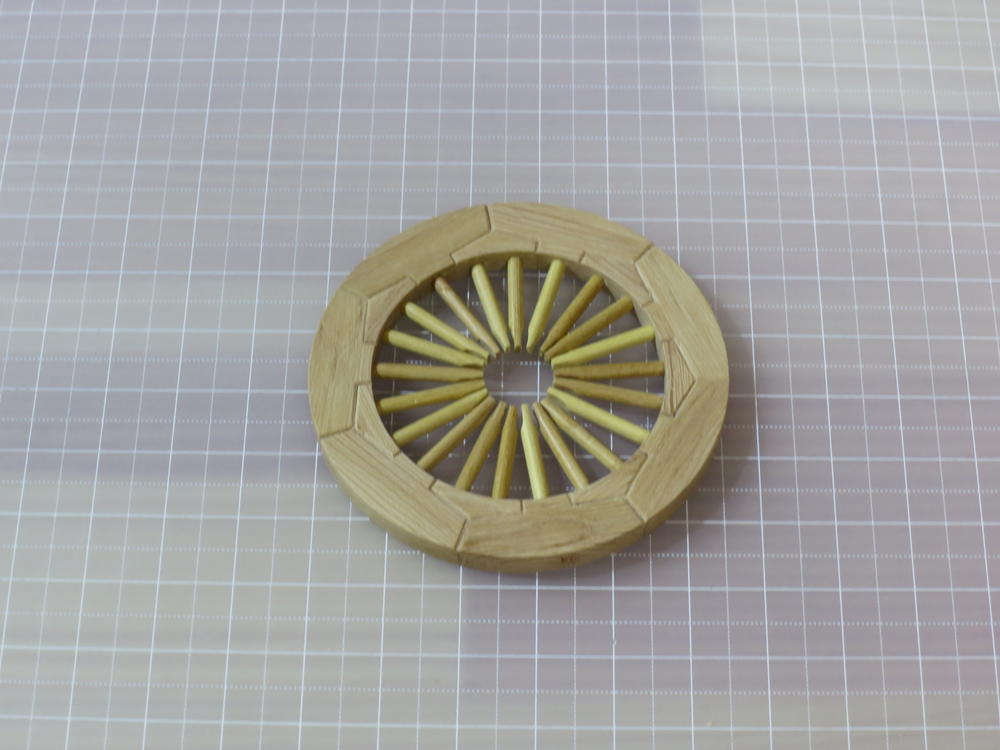最近のカメラやレンズは、手ぶれ補正の性能が上ってきました。また、花の撮影では、絞りを開け気味にすることが多く、高速シャッターが切れることが多いです。
そういうことから、手持ち撮影も十分可能で、そのほうが機動性に優れ、合理的なのかもしれません。
私の場合、メインで使うレンズに手ぶれ補正(IS)がついていないので、手持ちはつらく、庭での撮影では、三脚を使うことになります。
バラは、樹木としては低木のイメージですが、剪定の仕方・仕立て方によっては、かなり高いところに花がつきます。私のところでは、花の咲く場所は、人の高さ、あるいはそれを超えることも珍しくありません。
花が高いところにある場合、一般の中型三脚ではしばしば高さが足りなくなります。目いっぱいに伸ばすと安定性の点でも問題です。
また、軽量化のため、カーボンなど、デリケートな素材を使っているものでは、バラのとげなどで引っかき傷がつくのは避けたいところです。
私は、庭での撮影の場合、大型三脚を使っています。集合写真などで、プロがつかっているような三脚です(国産品です)。4段の三脚で、最大に伸ばすと、2メートルを優に超えます。
重くて大きいですが、移動距離が少ないので何とか扱えます。

(大型三脚での撮影:黄色の花はグラハム・トーマス)
これを 1~1.5段伸ばすと、たいていの高さはまかなえます。長く伸ばすと、小さな株は、またぎ越すこともできます。安定感もあり、エレベーターを長く伸ばしても撮影できます。3つの脚の開き角度にも自由度があります。
全段伸ばすことは極めてまれです。そこまで延ばすと、ファインダーをのぞくのに脚立では足りず、園芸三脚に乗っての撮影になります。
問題は、特に低い場所に咲いている花を写す場合で、大型三脚の場合、脚を広げても、エレベーターの長さよりは低くならないので、この場合は別の三脚を使う必要があります。
エレベーターの下側に雲台をつける方法もありますが、別の中~小型三脚を使う方が簡便だと思います。
上掲の写真で脚に巻いてある青いものは、自転車用のバーテープです。かなり分厚いです。以前はテニスラケット用のグリップテープを巻いていましたが、今回、試しに変えてみました。
カメラの側を、三脚でいくらしっかり固定しても、花のほうは、風が吹くたびにゆらゆらと揺れます。
とくに、風の通り道のようになっている場所は、いつまでも揺れが止まらない、といった状況になります。
こればかりは、根気よく待つよりありません。